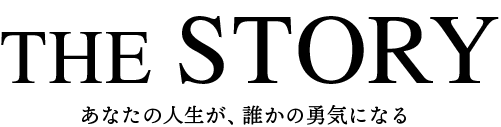動物たちから見えた世界は
様々な愛に満ちていた。
ボクがしっぽを振るたび、あなたは笑った。
ボクがあくびをすると、あなたは幸せそうだった。
その優しい目に映ったあなたの姿、
ずっと一緒にいた時間を映像で残す。
ただの“ペット動画”ではなく、
あなたとこの子だけの時間を、
動物の視点と、あなたからの視点、
それを美しく、そして感動的に
映像に残しませんか。
どれもあなたにとって、
永遠に残しておきたい思い出です。

Fit
このような方へ
大切なペットとの日常を、ただの写真や動画ではなく、物語として残したい。
家族みんなでペットと遊ぶ笑顔や、何気ない日常を映像で残しておきたい。
ペットと過ごす時間を、いつか振り返った時に心温まる形で見たい。
Features
特 徴

オーナーとの自然なふれあいを撮影し、“愛”を映像で表現。

ペットの表情・仕草を丁寧に記録。飼い主自身の変化や成長も含めた物語構造。

写真撮影も同時に対応し、映像と写真の両方で思い出を保存。

映画的映像美で、“思い出”が“物語”に。
「この子がいてくれるから、私は笑っていられる。」
そんなあなたの想いを、未来の宝物にします。
無邪気に駆け回る姿、甘えるしぐさ、ふと見せる優しい目。
その一瞬一瞬を、映像で永遠に残します。
メッセージ
ペットとあなたの本当の姿を映像に
動物たちとの幸せな暮らしを望む飼い主のみなさん、その日常的な様子を、まるで一つのドキュメンタリー映画のように記録してみませんか。
今まで頑張ってきた自分へのご褒美として、明日からの豊かなペットライフのきっかけとして。
ペットのイキイキとした姿、声、仕草、空気感を色あせることなく映像に残してみませんか。
僕自身も動物と暮らしていて、「ただのペット」じゃなくて、「一緒に生きてるパートナー」だなって日々感じてるんですよね。
この企画では、動物のかわいさや仕草はもちろん、飼い主さんとの関係性とか、その背景にあるストーリーなんかも自然なかたちで映像に残していきたいと思っています。
お話を聞かせてもらいながら撮影するのもありだし、動物目線で静かに見つめるような映像にしてもいいと思ってます。
【納品】
・映像は、完成作品に加えて、撮影した素材はまるごとお渡しします。
・写真も同時に撮っていくので、きっといろんな表情が残せるはず。
・スナップっぽく撮るというより、「そのままの自然な姿」を大事にして撮影しています。

表現したいのは
ペットの「かわいさ」
だけでなく、
人との関係性の深さ。
Case
事 例
short sample(01:31)
優しい一日。
パソコンに向かっていると、いつのまにか視界の隅にふわりと現れる。
キーボードの上に乗っかって、あたりまえのような顔で座り込む。
その小さな妨害に、心がほどけてしまう。
仕事の緊張も、せかされる時間も、そのしっぽの動きひとつでほどけていく。
やがて彼女は、飽きたように立ち上がり、
何かを確かめるように部屋をひとめぐりして、
ストーブの前にある、いつもの場所に静かに身を沈める。
彼女がいるだけで、部屋の空気がやわらかくなる。
あたたかい毛並みも、自由気ままな動きも、
全部が、今日という日を「やさしい一日」にしてくれる。
うちのねこ
short sample(01:30)
激しい一日。
冷たい空気を胸いっぱいに吸い込んで、足元の雪を確かめるようにひと足、ふた足。
リードを外すとき、彼の目は少しだけこちらを振り返る。
「いいの?」とでも言うように。
そして、許可の合図を感じ取ると、風のように走り出す。
畑一面を覆った真っ白な雪の上を、自由そのものの姿で駆け抜ける。跳ねるたびに雪が舞い上がって、まるで空に白い羽が舞っているよう。
それでも、呼べば必ず振り返る。
耳がぴくりと動き、体の向きを変えて、まっすぐにこちらへ駆け戻ってくる。その姿が、なによりもうれしい。
走ることが彼の喜びで、呼ばれて戻ることが、私たちの絆。
雪の上に描かれたその足跡は、
今日という日のしあわせな証しみたいだ。
うちのいぬ
言葉のない会話でも、
通じ合える日々。
その温もりを、
映像という優しい時間に
閉じ込めて。
Plan
プラン
人とペットの特別な絆を映像化。
単なるかわいらしい姿の記録ではなく、人間がペットに投影する思い、日々の何気ない瞬間に宿る深い関係性、そして「共に生きる」ことの意味を探究します。




活用方法
・ペットメモリアルサービスでの活用
・家族の宝物として保存
・ペットロスに備えた心の準備
・SNSでも共有できるダイジェスト版の提供

Voice
お客様の声
「ただのペット動画じゃない。“家族の物語”になっていて驚きました。」
「映像を見るたびに、“今ここにいる”ような気配を感じられるんです。
シニア期を迎えた愛犬との時間が、未来の宝物になりました。」
「夫婦の会話が減っていた時期に、“この子”がいる意味を思い出させてもらいました。」